皆さんは、2025年の大阪・関西万博(以下、万博)の「テーマ」について考えたことがありますか?
万博が掲げるテーマはいのち輝く未来社会のデザイン(Designing Future Society for Our Lives)。
これは、史上初めて“いのち”をテーマにした万博です。
ちなみに、1970年の大阪万博では「人類の進歩と調和」が掲げられました。
当時の日本が成長の象徴だった時代を思えば、まさにその言葉どおりだと思います。
万博が示す未来社会は、私たち大学生の学びや行動にもつながっています。
本記事では、20回以上通った大学生の視点からこのテーマをどう理解し、大学生活にどうつなげられるのかを考えていきます。
大学生として万博を体験して感じたこと
初めて大阪・関西万博へ行ったとき、正直「ただの大きなイベント」だと思っていました。
しかし、何度も足を運ぶうちに、万博が単なる大きなイベントではなく、「いのちが輝く社会のデザイン」に沿った「未来社会の実験場」という大きな目的を持つことに気づきました。
ここで言う「未来社会の実験場」とは、未来の暮らしや社会の仕組みを実際に試してみる場所ということです。
会場全体が、未来の社会システムを実験的に体験できるフィールドとして設計されています。
そして、その実験の中心にあるのが、万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」。
これは、技術や経済の発展だけでなく、人と自然、社会とテクノロジーが調和しながら“いのち”を大切に生きる社会をどう形づくるかという問いかけなのだと感じました。
万博会場では、この「未来社会の実験」が、技術・デザイン・行動などさまざまな形で展開されています。
特に印象に残ったのは、「持続可能性」をどのように具体的な形で実現しているかという点でした。
それは大きく、「仕組みの変化(技術・設計・エネルギー利用)」と「人の行動の変化(社会的な意識)」の2つに分けられると思います。
仕組みの変化
ここでの「仕組みの変化」とは、「社会の仕組みや技術、エネルギーの使い方そのものを変える取り組み」のことです。
「環境への負荷を減らしながら、持続可能な社会基盤をつくる」こと。
つまり、万博会場全体を未来の社会モデルとして設計し、技術とデザインの力で持続可能性を実現しようとする狙いです。
万博会場で実践していた「技術・設計・エネルギー利用の変化」を促す仕組みとして以下のようなものがありました。
- 木材や竹で作られたイス
- 会場内のあちこちに「給水スポット」を設置(マイボトル利用促進)
- 回収したCO₂からeメタンを生成
- 再生可能性エネルギーの活用
人の行動の変化
ここでの「人の行動の変化」とは、「人々の意識や行動スタイルの変化に関する取り組み」のことです。
「一人ひとりの行動を変えることで社会全体をより持続的にする」こと。
つまり、万博会場をモデル社会として、来場者が新しい行動様式を体験する狙いです。
万博会場で実践していた社会的な行動変化を促す仕組みとして以下のようなものがありました。
- エスカレーターの「歩行禁止」
- 完全キャッシュレス決済
- 分別の徹底
大学生視点で読み解く『いのち輝く未来社会のデザイン』
『いのち輝く未来社会のデザイン』とは何を意味するのでしょうか?
大阪府のwebページには、こう書かれていました。
「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマは、人間一人一人が、自らの望む生き方を考え、それぞれの可能性を最大限に発揮できるようにするとともに、こうした生き方を支える持続可能な社会を、国際社会が共創していくことを推し進めるものです。
https://www.pref.osaka.lg.jp/o030010020/bampaku_suishin/2025expo/index.html
この、文書を更に深堀していきたいと思います。
『いのち輝く未来社会のデザイン』を4つのキーワードに分けられると思います。
| キーワード | 意味 |
| いのち | 単に生物としての命ではなく、人・自然・技術・社会のすべてを含む |
| 輝く | 誰かが特別に成功することではなく、一人ひとりが自分らしく生きることを指す |
| 未来社会 | 単に“未来のテクノロジーが進んだ世界”ではなく、次の世代と一緒に生きる社会を意味している |
| デザイン | 単なる見た目でなく、仕組みそのものを創ること |
ここでの「次の世代と一緒に生きる社会」とは、環境・福祉・教育・技術など、分野を超えて誰も取り残さない仕組みを指してます。
これらを整理すると、「いのち輝く未来社会のデザイン」とは次のように言い換えられます。
「一人ひとりが自分らしく生き、その生き方を支え合う社会の仕組みを、みんなで作ること」
つまり
「個人の意識の変化」×「社会全体の持続可能性」
の両立が大事なのです。
大学生活にどう繋げられるか
では、私たち大学生はこのテーマをどう日常に活かせるでしょうか。
ここでは4つの例を紹介します。
知識をつなげて学びを広げる
大学では専門分野を深めることが求められますが、同時に学び同士をつなぐ力も大切です。
たとえば、環境技術を学んでいる人は、社会制度や経済の視点を少し取り入れるだけで、見える世界が変わります。
それは、単なる「勉強」ではなく、未来社会を自分の手でデザインする思考にほかなりません。
学問をつなげる意識が、未来を形づくる第一歩です。
小さな挑戦を繰り返す
万博に何度も通う中で感じたのは、行動すれば視点が変わるということ。
同じように、大学生活でも「行ってみる」「話してみる」「参加してみる」など、ほんの少しの行動が思わぬ気づきや出会いを生みます。
たとえ結果がすぐに見えなくても、その小さな挑戦の積み重ねこそが、自分なりの未来をデザインする力につながるのです。
小さな行動で社会を変える
一人ひとりの小さな行動も、積み重なれば大きな力になります。
それがやがて、社会の当たり前を変えていくのです。
たとえば
- エスカレーターの「歩行禁止」
- マイボトルの利用
- 分別の徹底
などがあります。
これらはどれも、特別なことではありません。
けれども、誰かが意識して実践することで、周囲の意識も少しずつ変わっていく。
大学生活で身につけたこうしたちょっとした行動の習慣は、社会人になってからも自分の価値観として残り続けます。
そしてそれが、「いのち輝く未来社会」を支えるにつながっていくのです。
人との関わりで世界を広げる
「いのち」は、孤立しては輝けません。
友人、先生、地域の人々、オンラインのコミュニティ――
多様なつながりの中でこそ、自分の学びや考え方は磨かれていきます。
大学生活は、人との関係をデザインする練習の場でもあります。
誰かと協力し、支え合いながら成長する経験が、これからの社会で求められる「共創」の力を育ててくれるのです。
まとめ
万博を通して感じた「いのち輝く未来社会」というテーマは、決して特別な話ではありません。
それは、私たち大学生が日々の学びや行動をどう“つなげる”か、どう“デザインする”かという問いそのものです。
行動すれば、学びが深まり、学びが人とつながり、つながりが社会を動かす。
その循環の中でこそ、自分の“いのち”が輝くのだと思います。
万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」は、大きな理想ではなく、大学生活の中で一歩ずつ実践できる小さなデザインでもあります。
万博が示した「未来社会のデザイン」とは、私たち一人ひとりが自分の生き方をどうデザインするかという問いかけでもあります。
その第一歩を、大学という小さな社会から始めてみませんか?
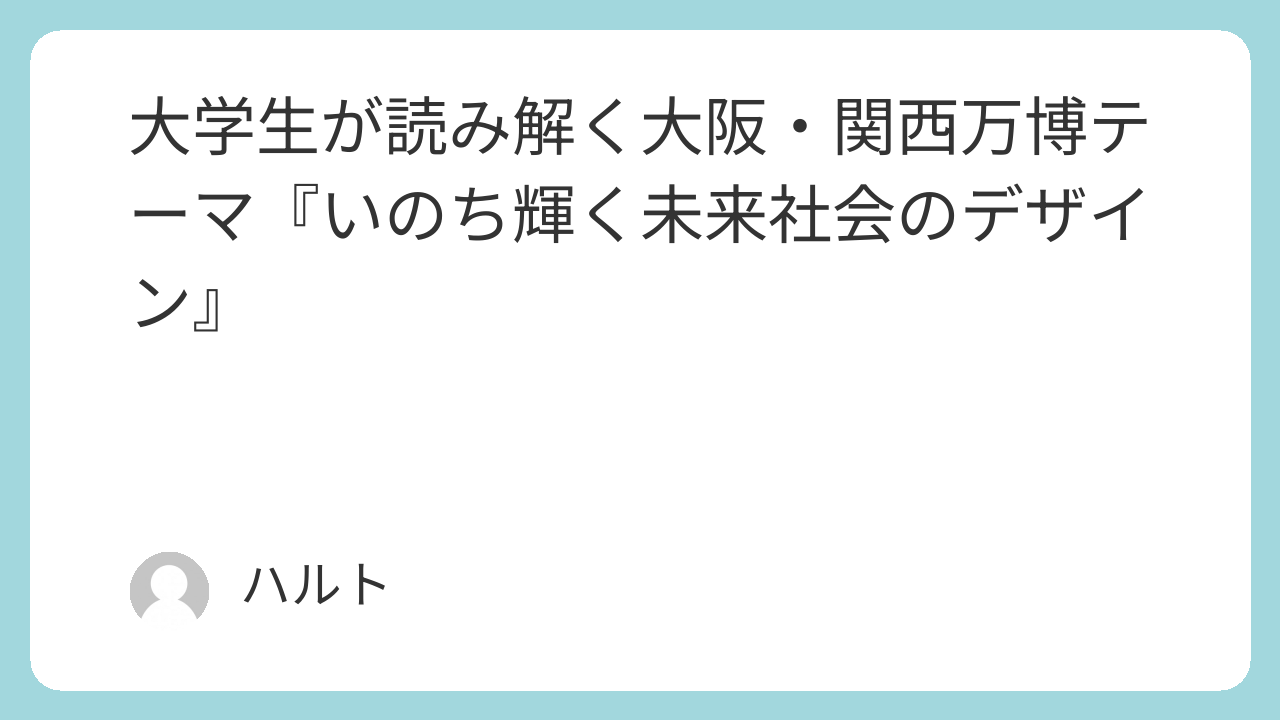
コメント